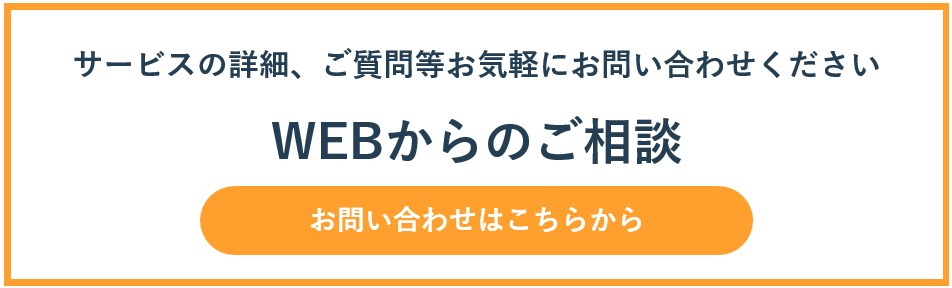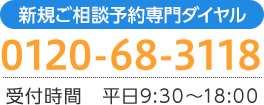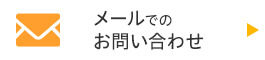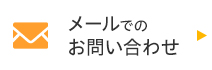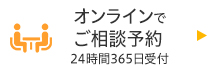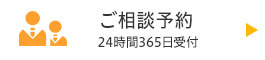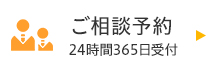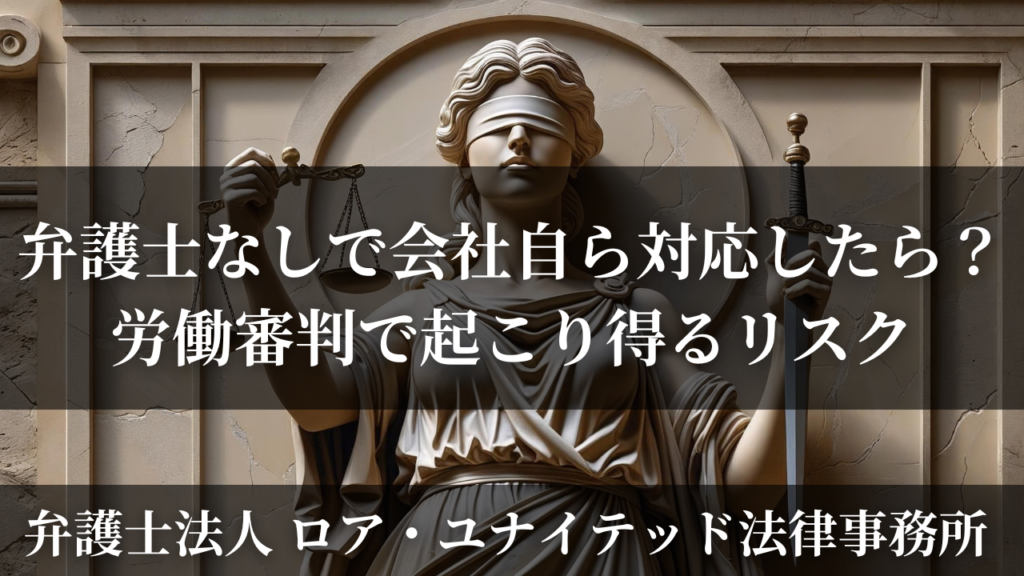
文責:岩野 高明
1 弁護士に委任せずに会社が自ら労働審判手続を行うことができるか
訴訟であろうと、労働審判であろうと、労働者から訴えられた会社は、弁護士に手続を委任することなく自ら裁判手続を行うことができます。ただし、会社が自ら訴訟行為をするためには、原則として代表取締役等の代表者が出頭しなければなりません。
会社法第11条1項では、「支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」と規定されていますので、支配人は代表者に代わって訴訟行為をすることができるのですが、この場合の「支配人」は、登記されている必要があります。訴訟に対応するために法務部長などを「支配人」として登記している会社は、非常に少ないでしょう。
もう一つ、労働審判に関しては、「裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる」という規定もあります(労働審判法第4条1項ただし書き)。しかしながら、この規定に基づき裁判所が弁護士でない者を代理人とすることを許可する例も、極めて少ないようです。
なお、労働審判手続では、事件に関わりのある会社関係者も裁判所に出頭し、手続に加わるのが通例です。この点は、弁護士に委任した場合でも、会社が自ら手続を行う場合(代表者が出頭する場合)でも同じです。労働審判手続において、出頭した会社関係者は、証人のような立場で、裁判所(労働審判委員会)からの質問に口頭で回答したりします。
このような事情から、比較的規模の大きい会社は、労働者から労働審判を申し立てられた際、弁護士に代理を依頼するのが通常です。これに対し、小規模の会社は、費用を節約しようとして、弁護士に委任せず自社で対応しようとすることもあるようです。
しかし、これはお勧めできません。その理由は、以下のとおりです。
2 労働審判手続の第1回期日までにしなければならないこと
労働審判を申し立てられた場合には、まずは労働者が作成した「労働審判手続申立書」を熟読し、争われている事実関係の中で、どの事実が重要なのか、どの事実が法律上意味を持つのかを正確に把握しなければなりません。労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理を終結しなければならない(労働審判法第15条2項)という、ただでさえ忙しい手続ですが、殊に同手続を申し立てられた会社側は、裁判所から申立書が届いてからわずか3~4週間程度で、これに対する「答弁書」を作成・提出することを強いられます。通常の訴訟手続に比べても、時間的な余裕はほとんどありません。
加えて、労働審判の場合は、通常の訴訟とは異なり、「答弁書」の内容次第で手続の方向性が有利にも不利にもほぼ決まってしまうという特徴があります。上記のとおり、労働審判手続は、建前では3回の期日が確保されますが、実際の運用では、「答弁書」を提出した後の第1回目の期日が非常に重要であり、第1回の失敗を第2回、第3回で挽回することは容易ではありません。第1回の結果が有利であれば、その後も有利な和解交渉をすることができますが、第1回がうまくいかないと、最終的な結果も不本意なものになってしまうことを覚悟しなければなりません。第1回期日に焦点を当てて全力を投入すべきです。
上記のとおり、答弁書の内容は重要ですが、これにも増して、主張した事実関係を裏付ける証拠を収集し整理する作業も重要です。会社側に有利な事実を答弁書でいくら主張しても、これを裏付ける証拠がなければ、当該事実の存在を裁判所(労働審判委員会)は認めてくれないかもしれません。訴訟や労働審判手続を多くこなしている弁護士は、経験上、どのような事実を証明するにはどのような証拠が有効かを熟知していますので、この観点からも、弁護士の助力を受けることは非常に有用です。
このようにして、定められた期限までに答弁書を提出し、併せて主張の裏付けとなる証拠を提出することになります。第1回期日がヤマ場ですので、この段階で主張できる事実をすべて主張し、提出できるすべての証拠を提出するのが理想です。
弁護士に依頼するメリットとしては、この時点(答弁書を作成する時点)で、手続の結末を見通せるようになることを挙げることもできます。労働事件を多く扱っている弁護士は、どの事実が認められればどの程度有利になるか、また、提出した証拠によって当該事実をどの程度証明することができているかといった点を熟知しています。重要な事実を証明できているのであれば、見通しは明るくなりますが、証明が不十分であれば、厳しい交渉を覚悟しなければなりません。第1回期日を迎える前に、自社がどの程度有利なのか、不利なのかを知ることができます。労働審判を和解(調停)で解決するのであれば、どの程度の解決金になる可能性があるのかは、会社にとって大きな関心事です。弁護士に依頼することによって、この点も明確になります。
3 第1回期日における裁判所への対応
以上のような準備をして、第1回期日を迎えます。労働審判手続では、労働審判官(裁判官)から会社の関係者に対し、ざっくばらんな質問が浴びせられたりもします。社内のルールの運用状況や、組織の形態、個々の仕事の内容など、事件に関係のありそうな事柄が訊かれます。この際、質問に戸惑ってしまったり、準備が不十分で答えることができなかったりすると、不本意にも労働審判委員会に不利な心証を抱かれてしまう可能性もあります。事前に弁護士から「このようなことを訊かれるかもしれないので、あらかじめ準備しておいたほうがよい」などと助言を受けることによって、慌てることなく質問に答えることができる可能性が高くなります。
このような手続を通して、労働審判委員会は、第1回期日において、事件に関するおおよその心証を固めます。
4 和解協議の巧拙の分かれ目
多くの労働審判手続では、早ければ第1回期日で、遅くとも第2回目の期日において、労働審判委員会が固めた心証に基づき、和解の協議へと手続が移行します。ここでも、弁護士が活躍することになります。
上記のとおり、経験が豊富な弁護士は、労働者・使用者のどちらが有利な状況かをある程度見極めることができます。労働審判手続は、3回の期日内で和解(調停)が成立しないと、労働審判委員会が労働審判を言い渡すことになりますが、その内容は、使用者が労働者に対して一定の金銭を支払うよう命じる場合が大半です。言い渡された労働審判に不服のある当事者は、2週間以内に裁判所に対して異議を申し立てることができますが、異議申立てがされた場合には、労働審判は効力を失い、事件は通常の訴訟手続に移行することになります(労働審判法第21条・第22条)。
和解協議の中で、弁護士は、(労働審判が言い渡され、これに対して異議申立てがされた場合の)訴訟の判決までをも見通して、和解交渉を主導していくのです。この和解交渉術こそ、会社が労働審判手続を弁護士に依頼する最大のメリットといえるでしょう。労働審判手続の中で、一定の解決金の額が提示された場合、経験のある弁護士は、その額が妥当であるのか、不当に高額であるのか、もしくは期待以上の好条件であるのかを、的確に判断することができます。この判断は、(労働審判手続が訴訟に移行した場合に)予想される判決内容と比較することによって可能となります。解決金が高すぎると思えば、より踏み込んで強気の交渉する必要がありますし、有利な金額であると判断すれば、これを受け入れて紛争を解決すべきです。
一方、弁護士に委任することなく、会社が自ら労働審判手続を行う場合には、知識の不足を付け込まれる可能性があります。殊に、労働者側に弁護士が就いている場合には、このような傾向は顕著です。それどころか、労働審判委員会ですら、和解(調停)を成立させるべく会社側に和解条件を受け入れるよう強く迫ってくることもあります。自社のポジション(有利な立場か、不利な状況か)を的確に把握したうえで交渉するのでなければ、押すか引くかの判断を誤る危険が高くなります。
5 まとめ
会社が労働審判を申し立てられた場合に、弁護士に依頼するかどうかの判断に迷った場合には、上記の事情を参考にしていただければと思います。第1回期日までの短期間に迅速かつ十分な準備をし、和解交渉においても的確な判断をするためには、弁護士を利用することを考慮に入れるべきでしょう。
▼関連記事はこちら▼
労働審判では初動対応が会社の勝敗を分ける!初動対応の重要性と適切な対応について弁護士が解説
労働審判の弁護士費用はいくらか?企業側が知るべき費用相場と費用対効果について解説
残業代・未払い賃金で労働審判を申し立てられた場合の会社側の対応について弁護士が解説
労働問題を未然に防ぐために早期に弁護士に相談する必要性について弁護士が解説
企業が労働審判で負けてしまう典型例とその理由について弁護士が解説
Last Updated on 2026年2月20日 by loi_wp_admin