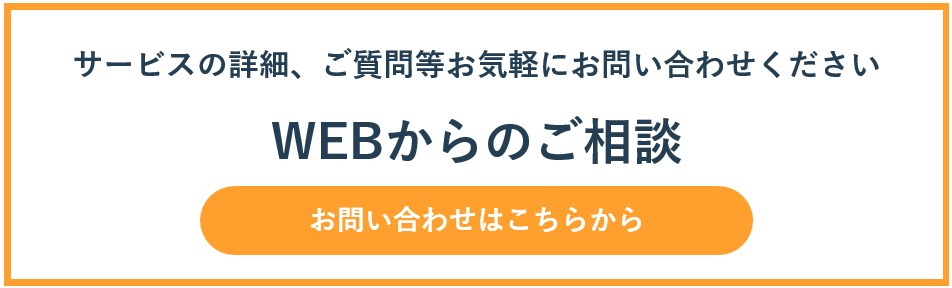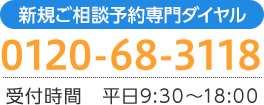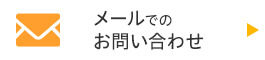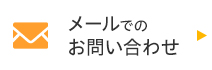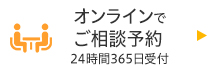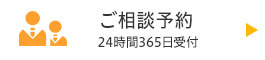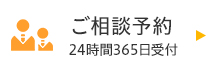文責:難波 知子
労災が起こった場合に会社行うべき対応の流れ
まず、労災の問題は、①従業員にケガや疾病、死亡という状態が発生、②従業員が労災申請、③労基署による調査(関係資料の確認、関係者への聴取、事業場の視察等)、④労基署長による支給または、不支給決定、⑤従業員からの民事上の損害賠償請求(交渉、調停、訴訟等)、⑥裁判内外の和解、裁判所による判決による流れをたどるのが一般的です。
一般的には、④の労基署長による支給決定が出た段階や、⑤従業員から損害賠償請求がなされた段階で弁護士に相談に来られる会社が多いと言えます。しかし、②の労災申請や③労基署による調査に適切に対応し、会社が正しいと認識している事実を適切に主張、立証しなければ、それとは別に行われる⑤従業員からの民事上の損害賠償請求の際に会社にとって不利な状態となり、莫大な賠償をせざるを得なくなる場面が生じえます。
以下、労災に関し会社が対応する場合の注意点、ポイントを説明します。
会社が労災対応する場合の注意点
(1)助力と証明が会社の義務とされていること
労災申請があった場合の会社の対応としては、労災として認識している場合はもちろんですが、労災とは考えていない場合であっても、申請について一定の助力をすることが義務付けられています(労災保険法施行規則23条)。
使用者として、従業員の健康被害が労働災害ではないと認識していたとしても、従業員の労災申請を止めることはできません。
具体的には、会社は「手続についての助力」と「必要な証明」が求められています。
(事業主の助力等)
1 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。
(2)手続についての助力義務
労災の申請は、本人が労働基準監督署長に、請求書を提出して行うことが原則です。
労災を申請するのは、労災を利用したい従業員本人であり、会社ではありません。
他方、事故のため自分で労災請求の手続が困難な従業員については、「事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。」とされています(労災保険法施行規則23条1項)。
このことから、労災申請は、会社が窓口となって申請の事務手続をサポートすることが一般的です。
(3)必要な証明の義務
労災申請にあたっては、一定の項目について事業主の証明を受けたうえで申請することが求められています。
たとえば、休業補償給付においては、「負傷又は発病の年月日」や「災害の原因及びその発生状況」等について事業主の証明を受けなければならないとされています(労災保険法施行規則13条2項)。
具体的に、請求書には、「事業主証明欄 」があります。ここに、「証明日」「事業の名称」「事業主の電話番号」「事業場の所在地」「法人名」「代表者名」等を記入して証明することになります。
▼関連記事はこちらから▼
製造業者が注意したい労務のポイントについて弁護士が解説!-雇用・労災におけるポイント-
建設業の労災で元請け責任を問われる場合とは?ケース別に弁護士が解説!
労災の事務手続の注意点
まず、会社が、従業員が申請してきた事故につき、労災と認識しており、記載内容が正しいのであれば、速やかに事業主証明欄に署名捺印します。
会社としては労災ではないと考えている場合、以下の各事項に注意して対応することになります。
①労基署に判断を任せること
会社として労災ではないと認識している場合であっても、従業員自身が労災申請することは自由であり可能です。したがって、会社としては、従業員の労災申請を妨害しないようにします。
会社としては、従業員には希望通り労災の申請をさせたうえで、労災かどうかについて、労働基準監督署長の判断を任せることになります。
従業員が申請した結果に労災にならないと判断されれば、会社としては、その結果を踏まえて、私傷病ということでその後の手続きを進めていきます。この場合、民事上の労災事故に基づく損害賠償請求もされ難くなりますし、実際訴訟提起された場合でも、業務との因果関係が否定され損害賠償請求が認められない可能性が高まります。
②安易に事業主証明欄に署名、押印しないこと
ア 事業主証明
会社が、労災にはあたらないと認識している場合には、労災申請の際の事業主証明欄の記載については慎重な対応をするべきです。従業員や、退職した従業員から労災申請があった場合に、会社が事実確認をしたところ、精神障害や、故意や業務を離脱時の事故等、会社としては労災ではないという判断になることもしばしばあります。
そのような状況下で「休業補償等の申請用紙に事業主証明をしなければならないでしょうか」という質問を会社からしばしば受けます。また、民事上の労災に基づく損害賠償請求をされた時点で、ご相談を受けた段階で、既に深く考えず、事業主証明をしてしまっているという事態にも遭遇します。従業員が事業主証明を求める「負傷又は発病の年月日」や「災害の原因及びその発生状況」につき、労災に助力しなければならないという認識で、会社が署名、押印してしまうと、書類上はその内容を認めたことになってしまいます。労災と認めていないのに、事業主証明をしてしまうと、その後の従業員からの民事の損害賠償請求において、事故や健康被害の発生や、業務と損害の因果関係を認める有力な証拠として利用されてしまいます。そしてその証明により、一度認めてしまった事実をその後否定するのは容易ではありません。
したがって、会社の側で、傷病は確認できない、業務との因果関係を肯定できないという合理的理由があれば、事業主証明はしないようにすべきです。
助力義務があるから証明したけど、その後民事上の損害賠償請求が行われ、事業主が証明したことでそれが訴訟上の証拠として使われてしまい困っているという相談は後を絶ちません。
イ 事業主証明できない場合の対応
証明できない場合には、署名押印をせずに、会社の見解を別紙(例えば、下記「労災保険給付請求書における事業主証明拒否について」)として整理したうえ提出することが適切です。
会社側でこのような扱いにしても、その後、労災か否かは労基署が判断するため、労基署が労災であると判断すれば、休業補償等が支払われます。事業主証明欄は記載しない場合でも、従業員による労災申請は可能です。本人が理解していないようでしたら本人にその旨説明するのが丁寧です。
拒否の際には、労災認定については、「労災認定基準」がありますので、基準を確認したうえで、労災には該当しない理由を従業員、労基署に論理的に説明していかなければなりません。
この点、署名拒否したが、結果的に労災申請が通った場合でも、その後提起された民事上の損害賠償請求訴訟において、労災申請拒否をしたことが有力な証拠となり、その因果関係が否定された事例もあります。会社としては、労災申請が通っても、民事上の損害賠償請求も必ず認められるわけではないということを認識しておき、そのためにできる限りの準備をしておくことが有用です。


③ 労基署からの調査(関係資料の確認、従業員及び関係者への事情聴取、事業所視察等)への対応を準備する
労災申請がされると、労働基準監督署からの調査が行われます。会社の見解を根拠づける調査、聞取り、資料を集めたうえで、整理して準備した上で、調査に対応することになります。
具体的には、関係資料(雇用契約書、就業規則、賃金規程、タイムカード、警備システムの記録、パソコンのログ等)の確認、従業員及び関係者(代表者、上長、同僚、部下)への事情聴取、事業場の視察等が行われます。会社としては、当然、「労災隠し」と疑われるような行為はしてはならず、労基署による調査には誠実に応じる必要があります。
労基署は従業員からの申請に基づき、調査が開始されていますので、従業員の主張に沿った事実に反した調査結果が出されることがないように、会社として指摘すべき事実関係や法的主張については十分に伝える必要があります。必要に応じて関連資料を追加で提出すべきです。
④ 意見申出制度を活用する
従業員の労災請求に、事業主側の意見を反映させる制度として、「事業主の意見申出」という制度があります(労災保険法施行規則23条の2)。
労災申請を知った早い段階で当該事案において労災認定の判断にあたって、会社の意見書を作成して、労基署に提出することになります。使用者として労働災害ではないと考えているケースであれば、会社側の主張をまとめた意見書の提出をすべきです。

⑤労災認定への対応
労基署長は、労基署による調査内容を踏まえて、支給決定又は不支給決定を行います。
労基署長の決定に不服がある場合、法律上は、労働保険審査官への審査請求、労働保険審査会への再審査請求、取消訴訟の提起という手段が用意されていますが、これは、処分の名宛人(すなわち、従業員側)が採ることのできる手段であり、会社は、原則としてこれらの手続きに関与できない、とされています。
メリット制に基づく法律上の利害関係を理由に使用者による取消訴訟の提起が認められることもありますが(東京地判平成29年1月31日 労判1176-65)、これは例外です。
このように、労基署長による支給決定後において、会社は、この決定に判断の誤りがあったとしても、これを争うことができません。一般的に、労災認定がなされてしまったケースの場合、会社の民事責任が肯定される可能性は高いため、民事責任のリスク回避のためにも、使用者側による積極的な対応は重要です。
▼関連記事はこちらから▼
心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正を踏まえた実務上の留意点を弁護士が解説!
労災申請を嫌がる会社が多い理由
労災申請は、単純に面倒だと考えたり、労災申請は会社の評判を落とすものと考えて単に拒否の気持ちが強いこともあります。
また、上記のとおり、会社は労災という認識ではないという場面もあろうかと思います。この場合、申請は従業員自身でできますし、その判断は労基署長によります。
病気やケガまた、死亡が業務によるものと認められて、業務災害の労災が認定されると、従業員やその遺族から会社に対する損害賠償請求が認められやすくなります。また、労災が認定された従業員の解雇が制限されます。会社の評判にも影響する可能性もあります。
従業員から労災で訴えられてしまった際の対応
従業員は、労災申請に対する労基署長とは全く関係なく、使用者に対し、労災事故についての安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求をすることが可能です。交渉、調停、訴訟という手段で請求がなされることが一般的です。
既に相当話がこじれている場合や話し合いの余地がない場合、また、従業員やその家族の希望から、いきなり訴訟提起という場合もありますが、まずは、裁判外での交渉にて請求がなされることも多いです。この段階で、請求額につき和解できれば、事案は公にならず、早期解決ができることから労使双方にとって大きなメリットがあるといえます。紛争がいたずらに長期化してしまうことは避けるべきです。
この点、労災認定がなされて支給決定が下された場合には、民事上の損害賠償請求がなされる可能性が高くなります。なぜなら、労基署長が事故の発生や業務との因果関係はあると判断したことになりますし、労災による補償は、従業員に生じたすべての損害を補填するものではないため(例えば、休業損害については、休業補償給付によって補填されるのは、給与の6割のみです。)、この金額を超える分については、使用者の民事責任を追及することで、損害の回復が図られるからです。
この時点で、労災ではないと会社が認識していたが事業主証明をしてしまった場合には、これも有力な証拠とされ、その段階から、事故や従業員の健康被害の発生、また、業務と損害の因果関係を否定し、それを立証するのは、不可能ではありませんが、相当困難になります。
従いまして、上記3で述べたとおり、事業主証明、その後の労基署への対応については、安易に従業員側の主張を受け入れず、会社の把握する証拠とそれに基づく主張を前提に慎重に対応する必要があります。
▼関連記事はこちらから▼
労働災害についての当事務所の解決事例
従業員がパワハラを主張して弁護士をつけて会社に損害賠償請求をした事案で、請求金額を大幅に減額して示談により解決した事例
【企業概要】
製造業、従業員規模 500名程度
【事案の概要】
従業員が、弁護士を代理人に立てて、上司からパワハラを受けたと主張して200万円の損害賠償請求をした事案でした。
労働災害について当事務所でサポートできること
当事務所は、ケガ、死亡事故、過労死、過労自殺、精神障害の労災認定事案につき、労基署の労災認定手続きに関与するだけではなく、民事上の損害賠償請求を提起された場合の対応も多数経験しております。労災認定がされた上での民事上の損害賠償請求訴訟につき、棄却という判決を得たことも複数回あります。
当事務所にご依頼いただいた場合、過去の和解経験、実際の裁判例の分析をもとにした今後の見通しを提供し、依頼者の会社様に最大限メリットがある対応につきアドバイス致します。判決での終結のみならず、早期の有利な条件での和解にて事件を終了させ、会社へのダメージを最小限に収めることを目指して対応しておりますので、是非ご相談ください。
Last Updated on 2024年5月3日 by loi_wp_admin